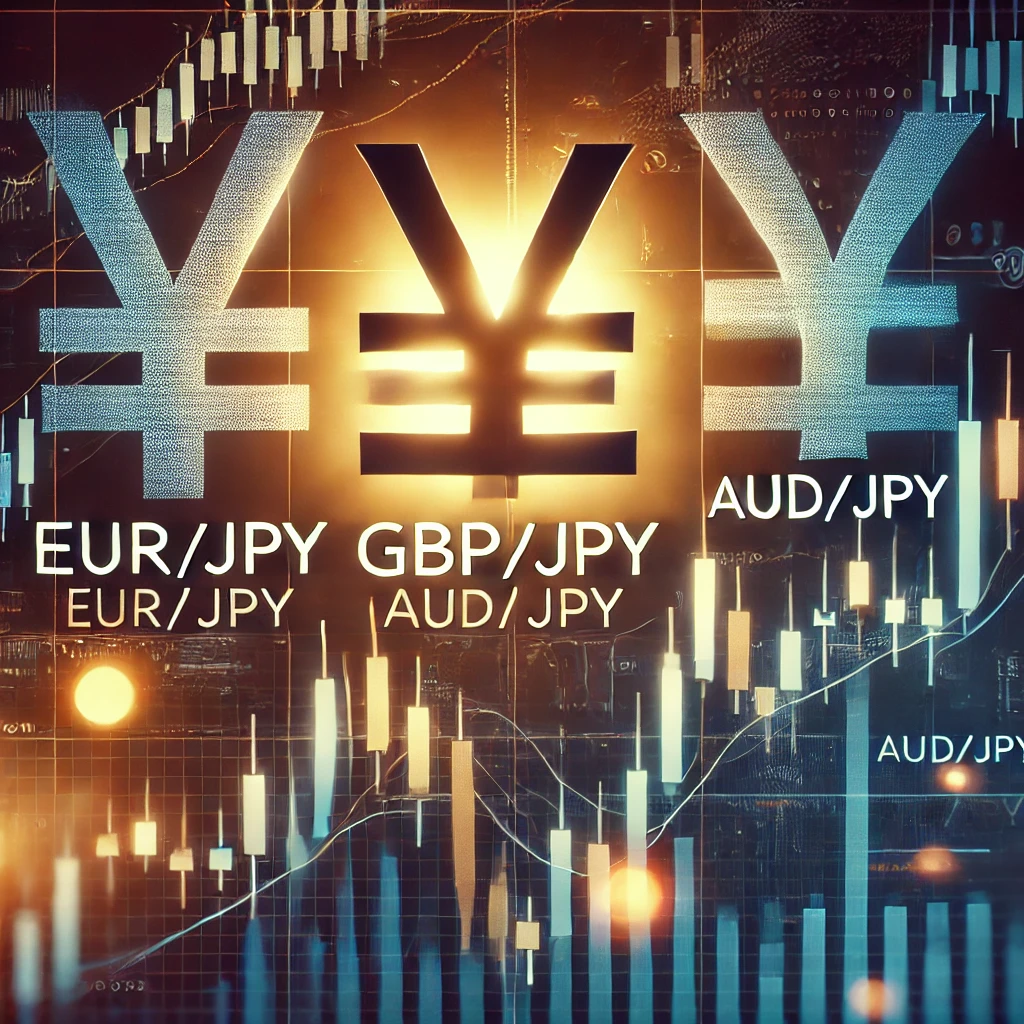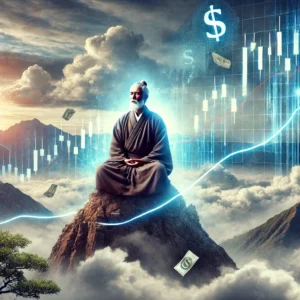FXをやっていると、「ユーロ円やポンド円はトレンドが出にくく、レンジ相場になりやすい」と感じることはないでしょうか? 特に1日単位で見ると、クロス円の通貨ペアが一定の範囲で上下することが多く、ナンピン戦略が機能しやすい場面が目立ちます。
この傾向がもし本当なら、なぜそうなるのか?今回はその理由を考察していきます。
クロス円はドルの影響を間接的に受ける
クロス円(EURJPY, GBPJPY, AUDJPYなど)は、直接取引されているのではなく、USDを介してレートが決まります。 例えば、ユーロ円(EURJPY)は次のように計算されます。
EURJPY = EURUSD × USDJPY
この仕組みにより、クロス円はUSDの影響を間接的に受けるため、 ドルストレート(EURUSDやGBPUSDなど)とUSDJPYの動きが相殺され、 値動きが抑制されることがあります。 その結果、1日単位で見ると、明確なトレンドが出にくくなり、レンジ相場になりやすいと考えられます。
東京市場は比較的安定している
FX市場は、
- 東京市場(9:00~18:00)
- ロンドン市場(17:00~2:00)
- ニューヨーク市場(22:00~7:00)
の3つの時間帯で動いています。 東京市場は、
- 欧米市場と比べてボラティリティ(値動きの幅)が小さい
- 日本の機関投資家(輸出企業・年金ファンドなど)が安定した取引をする
といった特徴があり、大きく動くことが少なく、レンジ相場が形成されやすいのです。
仲値(9:55)前後の影響
日本の銀行は毎朝9:55に「仲値」というその日の基準レートを決定します。 この影響で、
- 仲値前に一方向へ動く
- 仲値決定後に反転する
という値動きがよく見られます。 つまり、日中は一定の範囲内で動くことが多く、 短期的なレンジが形成されやすいのです。
投機筋(ヘッジファンドなど)の影響がドルストレートより少ない
ドルストレート(EURUSD, GBPUSDなど)は、 機関投資家やヘッジファンドが積極的にトレードするため、 大きなトレンドが発生しやすいです。
一方で、クロス円はそこまで投機筋の影響を受けにくいため、 急激なトレンドが発生しにくく、短期的にレンジを形成しやすいのです。
ユーロ円・ポンド円・オージー円の特性
クロス円の中でも、それぞれの通貨ペアには特徴があります。
- ユーロ円(EURJPY):比較的安定した値動き。長期トレンドは出やすいが、1日単位では方向感が出にくい。
- ポンド円(GBPJPY):ボラティリティは高めだが、短期的には上下に振れやすく、レンジを形成しやすい。
- オージー円(AUDJPY):資源国通貨の影響でリスクオン・オフで動きやすいが、1日単位では大きなトレンドになりにくい。
このように、クロス円の特性を考えると、 短期的なレンジ相場を活用したトレードが有効になることが多いのです。
市場参加者のポジション調整
クロス円の値動きは、各市場のトレーダーがポジションを調整することで生じます。
- 東京市場では機関投資家の取引が多く、方向感が出にくい
- 欧州時間でボラティリティが増すが、一定の範囲で往復しやすい
- ニューヨーク市場でドルストレートの影響を受けるため、クロス円の動きが鈍る
このため、1日単位では上下に動きながらレンジを形成することが多くなります。
ナンピンが効きやすい理由
クロス円のレンジ相場が多いことから、ナンピン戦略が有効になりやすいです。
- 値動きが往復しやすい → ナンピンしたポジションが救われる可能性が高い
- 東京時間のレンジ傾向 → 短期の逆張りが機能しやすい
- 仲値の影響で値動きが一巡しやすい
- サポート・レジスタンスが意識されやすい → テクニカルが機能しやすい
特に、東京市場ではレンジが続くことが多いため、 ナンピンを活用した逆張りトレードが有効になる可能性が高いです。
まとめ
クロス円(ユーロ円・ポンド円・オージー円)が1日単位でレンジになりやすい理由として、
- ドルを介するため、動きが緩和されやすい
- 東京市場の影響で短期レンジが発生しやすい
- 仲値の影響で値動きが一巡しやすい
- 投機筋の影響が少なく、レンジ形成が多い
- 市場参加者のポジション調整で、往復の動きが出やすい
といった点が挙げられます。
この特徴を活かせば、 東京時間のレンジを利用したナンピン戦略や逆張りトレードが有効になるかもしれません。
もしクロス円でのトレードを検討しているなら、 この傾向を参考にして、ナンピン戦略を活用するのも一つの手かもしれません。